6月12日から25日に行われた6月定例会の中で、諸報告として「行政経営プラン」についての説明がありました。
このプランは、高砂市の“人・モノ・カネ”という経営資源をどう活用していくかを整理したもので、まちづくりや行政運営の土台ともいえる重要な計画です。
この報告に関連して、私は人口減少への捉え方について質疑を行いました。
高砂市の人口は人口ビジョンの目標以上に減少しており、転入超過である0歳~9歳については、依然転入超過ではあるものの、その超過具合は減少していることが現状です。
これまで、高砂市は0歳~9歳が転入超過であることから、「子育て世代には選ばれている」という考えも示していましたが、コロナ禍以降、そうとも言えない状況が続いています。
行政経営プランの中では、人口減少とりわけ20代の転出超過が課題として挙げられています。
その対応策を質問したところ、市長からは「駅前整備による定住促進」が述べられました。
駅前整備を人口減少対策として行うことについては、以前から私は疑問に思っています。
<過去ブログ>都倉市長任期2期目初の施政方針が示されました
また、市長の考えとしては、駅周辺を整備することによって、高砂から若い世代が流出しなくなるということでしたが、
私の考えとしては、大学がない高砂市としては、20代ではむしろ進学や就職で外に出ていくことも考慮した上で、30代、40代になって戻ってこれるまちを目指すべきではないかと考えているため、その考えも提示しました。
このことについては、市長からは「確かに進学や就職などで転出していることは承知しているが、それでも駅周辺の整備を通じて、通勤・通学しながらでも市内に住み続けられる環境を整え、転出超過を抑えていきたい」ということが示されました。
さらに、今回の議論の中で政策部長からは、「これまで“人口”を最上位の成果指標としていたことは、反省点であり、現在策定中の総合計画では、“幸福度”を成果指標としていきたい」ということが示されました。
ただ単に「人を増やす」ことをゴールにするのではなく、今住んでいる人が安心して暮らし、自分らしい幸せを実感できるまちにしていこうという方向性には、私も賛成します。
一方で、“幸福度”という言葉はとても広く、抽象的なものでもあります。
誰の、どんな幸福を指すのか。どうやって測るのか。どんなふうに施策に活かしていくのか。
今後、こうした点を議会の審議を通じて明確にしていければと思います。





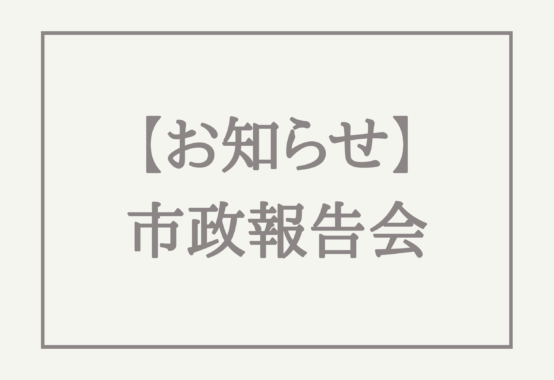







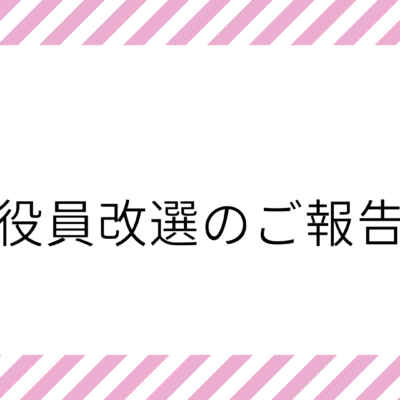

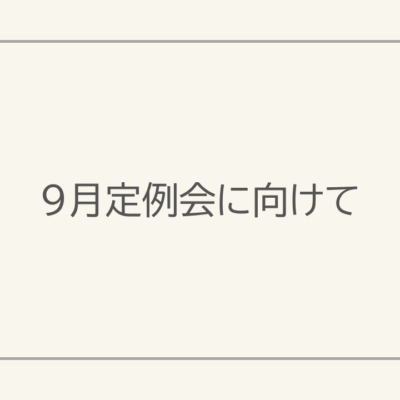





この記事へのコメントはありません。