先日、北海道室蘭市にて、「コンパクトシティ」に関する取組を学びました。
室蘭市は北海道内で最も面積の小さい自治体であり、港町として、そして鉄鋼業を中心に発展してきた歴史を持っています。
<視察資料>室蘭市「地方再生コンパクトシティの取り組みについて」
室蘭港は明治5年(1872年)に開港し、石炭の積出港として発展しました。
その後、日本製鋼所や北炭輪西製鉄所の立地によって鉄鋼業のまちとして栄えましたが、鉄鋼不況を経て特殊鋼へとシフトしてきました。
現在も日鉄やジェスコなど大手企業が拠点を構え、地域経済を支え続けています。
ちなみにジェスコは行政主導の企業誘致で誘致を行った企業とのことでした。
そうした産業都市としての歴史を持ちながらも、人口減少や財政の制約といった現実に直面する中で、室蘭市は「立地適正化計画」「都市計画マスタープラン」「地域公共交通網形成計画」に基づき、都市機能を集約しつつ交通ネットワークで結ぶ「コンパクト・プラス・ネットワーク」による持続可能なまちづくりを進めていました。
拠点となる地域に公共施設や住宅を誘導し、効率的なバス路線を再構築し、拠点間を公共交通で結ぶことによって、暮らしやすさを保とうとしている姿勢が印象的でした。
特に力を入れているのが、室蘭駅周辺地区での都市再生とのことです。
このエリアでは、図書館や青少年科学館、総合体育館といった公共施設が老朽化し、かつてにぎわった商店街も衰退していました。
また、国の登録有形文化財である旧室蘭駅舎をどう活用するかも大きな課題となっていました。
こうした状況の中で、室蘭市は社会資本整備総合交付金を活用し、公共施設の集約や再整備に取り組まれていました。
図書館と環境科学館を一体化した「えみらん」という施設を整備し、延床面積を抑えながら市民サービスを維持する工夫をしているほか、スポーツ施設を運動公園に集約するなど、公共施設の効率的な配置を進めています。
さらに、旧室蘭駅舎と隣接する公園を一体的に整備し、SLの展示やイベント開催を通じてにぎわいを生み出そうとしていました。
こうした取組によって、新しい公共施設では利用者数が増加し、商店街でも空き店舗の活用が進んだとのことでした。
オープンスペースを使った市民活動も広がり、継続的なにぎわいづくりにつながっているとのことです。
市民や学生が主体的にイベントを企画し、まちなかに人を呼び込む動きが芽生えているのも大きな成果だと感じました。
一方で、公共施設の利用者をどうまちなかへ回遊させるか、また民間や市民と行政がどのように協力し合っていくかといった課題もあるとのことでした。
今回の視察を通じて学んだのは、単に老朽化した施設を建て替えるのではなく、まちのグランドデザインはもちろんのこと、住民の生活圏を意識し、公共交通との連携まで含めて戦略的に進めることの重要性です。
そして、公共投資に加えて市民活動や民間の発想を掛け合わせることで、持続的なにぎわいにつなげていくという考え方が、高砂市にとっても大きなヒントになると感じました。
高砂市でも、公共施設の再編やまちの活性化は避けて通れない課題です。
室蘭市で得た知見をしっかりと活かしながら、これからのまちづくりを考えていきたいと思います。




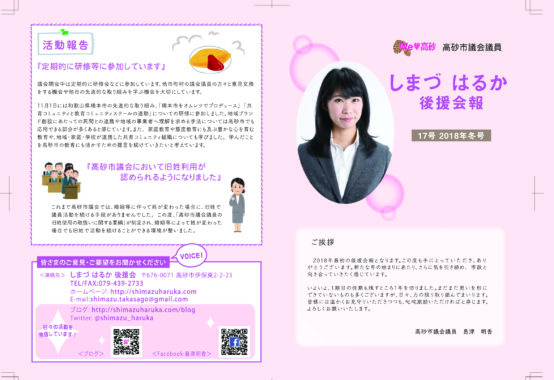








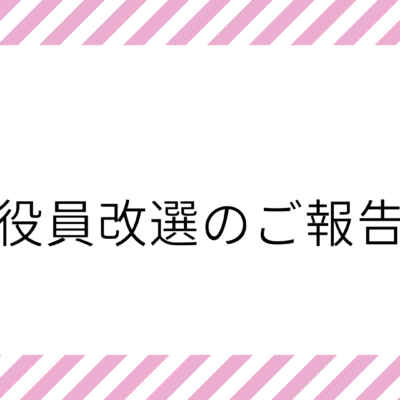

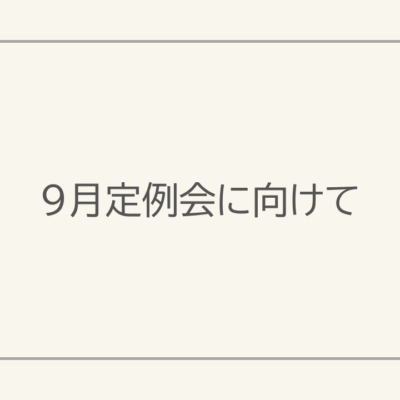





この記事へのコメントはありません。