先日、「自治基本条例と住民自治の今後のあり方について」という研修を受講しました。
講師は元逗子市長であり、大学教授として地方自治を研究されてきた富野暉一郎氏。
住民自治のあり方を長年現場と学問の両面から見てこられた方です。
自治基本条例とは?
自治基本条例は「まちの憲法」とも呼ばれます。
市民・議会・行政それぞれの責務を定めることで、まちづくりの土台となる考え方を共有するためのものです。
ただし「作ること」自体が目的になってしまっているもの課題です。
条例があることで初めて、行政には説明責任や検証の義務が課され、市民は行政に対して「条例違反ではないか」と問いかける根拠を持てます。
本来は、市民が使うことのできる道具の一つであると考えます。
かつて「流行」した自治基本条例
この条例は、1999年の地方分権一括法をきっかけに、2000年代に全国で一気に広がりました。
当時は「まずは作ること」という空気もあり、多くの自治体が競うように制定しました。
しかしその後、運用や検証が伴わず形骸化してしまった例も少なくなく、現在では新たに制定する動きは落ち着いています。
今は「どう使うか・どう活かすか」が本当の課題になっていると感じました。
人口減少時代の自治
研修では、人口減少時代における自治の規模についても議論がありました。
小さな自治体が単独で医療や教育などを維持するのは難しい現実があります。
だからこそ「合併」だけではなく、連合や事務の広域的な分担など、柔軟な組み合わせが必要になるというお話がありました。
高砂市での可能性
高砂市には現在、議会基本条例はあっても自治基本条例はありません。
これまで、流行りに限らず今日に至るまで多くの議員が提言はしてきている経緯があります。
このまちの未来を市民とともに考えるためには「共通のルール・合意」をつくることも大切ではないかと感じます。
- 市民が主体的に声をあげられる場を保障する
- 行政に説明責任を果たさせる根拠となる
- 将来世代のために、まちの方向性を共有する
こうした役割を担えるのが自治基本条例です。
もちろん、つくるだけでは意味がありません。
つくるのであれば、市民と行政が一緒になって「活かす」ことが前提であると考えます。
研修を通じて、自治基本条例は「作るか作らないか」ではなく、「どう使って、どう住民自治を育てるか」が問われていることを学びました。
高砂市にとっても、市民と行政が協働して未来を形づくるための一つの可能性として、本質をとらえて議論していく価値があると感じています。


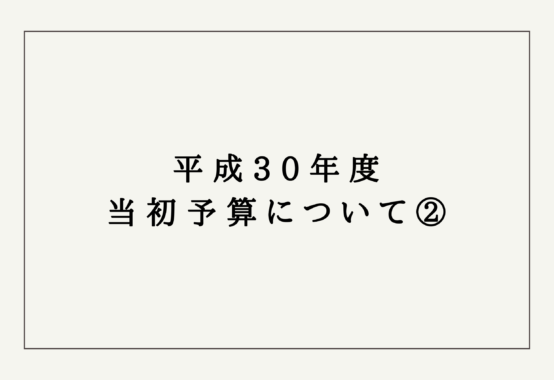

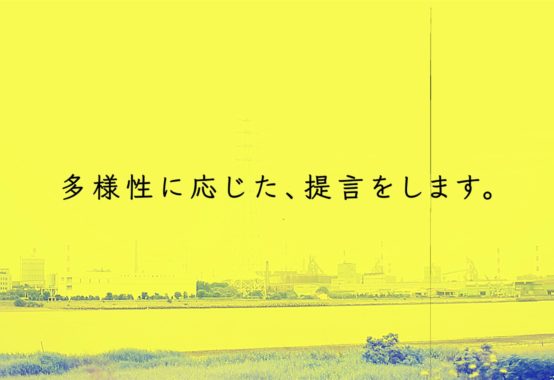








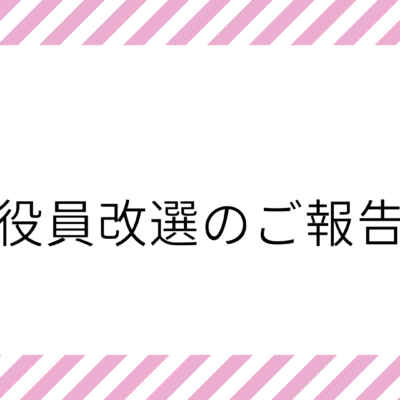

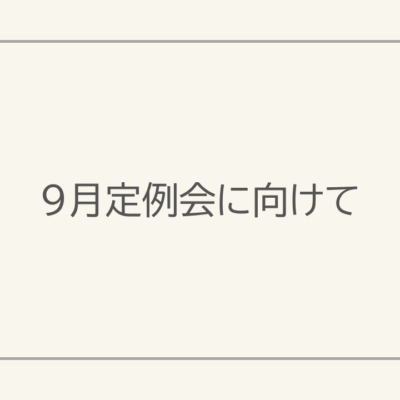





この記事へのコメントはありません。